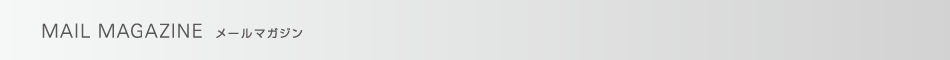地域包括ケアを支える次世代型歯科医院【1】コミュニティを創る歯科医院
2018年09月28日
「外来氷河期がやって来る!10年後を見据えた診療所生き残り策」と題した特集を、医療・介護の経営情報誌「日経ヘルスケア」(日経BP社)が掲載したのは2016年11月号でした。
特集記事では外来医療需要は2025年にピークを迎え、その後、減少に転ずるという見通しについて解説されていました。
また、2016年7月~8月にかけて日経メディカルOnlineの診療所開業医会員を対象に実施された調査で、既に外来患者の減少を実感している開業医たちが出始めていることが分かったとも書かれていました。
その上で、診療所の生き残り策の事例の一つとして、歯科医院と連携し、歯科医師による嚥下機能の評価や嚥下リハビリなどを行っている内科クリニックが紹介されていました。
3年に一度公表される厚生労働省の患者調査によれば、2014年の時点で歯科診療所を受診する患者の41%が65歳以上となっています(図1)。

1990年の13.4%から約30年で患者の高齢化率は3倍になったことになります。
団塊の世代の患者が80歳を超えて、通院が困難となり、さらに、若年層の人口減少が進めば、歯科医院の経営への影響は計り知れません。
経営学者ドラッカー流にいえば、これは「すでに起こった未来」なのです。
患者減少が表面化し、いまよりさらに深刻化する前に、高齢化する患者のニーズに合わせた診療体制や診療内容の見直しは急務です。
また、定期的に口腔健康管理で通ってくれることで歯科医院を支えてくれた高齢患者に対する責務でもあります。
超高齢社会の歯科需要の将来予想を視野に入れて、診療体制や診療内容を替えるという歯科医院のビジネスモデルの転換には「異業種の知恵」が参考になります。
雑誌「公衆衛生」(医学書院)は、2017年11月号で「薬局・薬剤師の地域展開~コミュニティ・ファーマシー」を特集しました。
また、小売・流通業向けの雑誌「ダイヤモンド・チェーンストア」(ダイヤモンド・リテイルメディア)が同時期に特集したテーマは「地域ど密着で克つ!コミュニティスーパー」でした。
いずれもコミュニティがキーワードとなっています。
コミュニティの拠点としての薬局、スーパーという視点で、人口減と少子高齢化の課題を抱える地域に根ざした体制整備を進めています。
なぜなら、薬局もスーパーも小売業の存立基盤は「地域」だからです。
ドラッグストアの大手の中には、店内に設けたコミュニティスペースで各種セミナーを開催するなどして、顧客の健康や美容をサポートする体制を整えているところもあります。
そこには、地域の抱える健康課題を解決するドラッグストアであることを顧客にアピールすることで、同業他社との差別化を図りたいという狙いがあります。
たしかに店舗を地域のコミュニティの拠点にする活動や地域貢献活動は、直接収益を上げる性質のものではありません。
しかし、健康格差対策でいま注目されている、地域の人たちのつながり力を表す「ソーシャル・キャピタル」を高めることに寄与することは間違いありません。
「コミュニティが顧客を連れて来る」という発想そのものです。
存立基盤が「地域」であることは医療機関も同じなので、医療の提供だけでなく、地域住民と多職種がつながるコミュニティづくりに取り組んでいる歯科医療機関も現れはじめました。
その一つが熊本市で開業43年目の添島歯科クリニック(添島正和院長)です(図2)。

開業以来掲げている「口福楽笑」という医院コンセプトを超高齢社会にふさわしい形に再定義し、新しく設けたコミュニティスペースで、ヨガ教室や食育教室、資生堂の化粧療法を活用したオーラルフレイル予防教室などを開催しています。
なかでも近隣の介護施設において、資生堂とのコラボによる口腔ケアとセットで開催したお化粧教室には、地元のテレビ局と新聞社も注目し、取材が入りました。
いまはコミュニティづくりの活動が、歯科医院の広報活動につながる時代なのです。
(有)Willmake143 代表
田中 健児