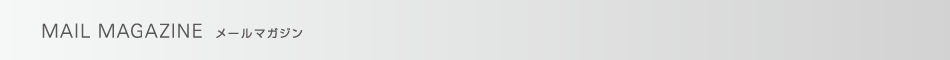【4】根管治療でのトラブル対策
2018年02月19日
数多く歯髄炎や根尖性歯周炎に対する根管治療を経験すると、
いろいろなトラブル症例に遭遇することになります。
このことが原因となり、
患者さんとのコミュニケーションがとれなくなることもしばしばです。
忙しい臨床のなかで、
一所懸命根管治療していて引き起こしてしまうこともあれば、
再治療歯などですでにトラブル事故が生じている症例を引き当ててしまうこともあります。
拙著『根管治療で失敗する本当の理由』のPart 2では、
後者のトラブル症例に対する対処法が解説されています。
具体的には下記のような項目です。
1.治療しても痛みがとれない
2.滲出液・排膿がとまらない
3.根管が狭窄・石灰化して、拡大・形成が難しい
4.歯根穿孔
5.器具破折
6.根管充填が難しい
臨床では原因究明や治療法選択などの局面で、
歯科医師の迅速かつ的確な判断が求められます。
現在、歯科医師の診療に大いに役立つ新しい診断・治療機器・器材、薬剤などが開発されています。
たとえば、歯科用CBCT、マイクロスコープ、Ni-Ti製切削器具、そしてバイオセラミックスなどです。
トラブル症例の解決策にも有効活用ができるのです。
●歯科用CBCT
歯科用CBCTは、従来までのデンタルX線写真やパノラマX写真では発見できない複雑部位を、三次元断面像で観察できるように開発された装置です。
未発見の根管や病変部の探索、穿孔部位の確認、器具破折箇所の探索、
さらに歯根吸収の範囲など、トラブル症例の術前・術中診断に貴重な情報を歯科医師に提供しています。
一方で、CBCTを臨床で活用する場合、限界を知ることも重要です。
デンタルX線写真は画像がシャープであり、
基本的情報が1枚の写真に含まれるといっても間違いではありません。
しかしCBCTの弱点として、
観察目的部位近くの金属や根管充填材によるアーチファクト(偽像)、
撮影時の患者さんの動きによるムービングアーチファクトなどにより、
CBCT画像は読像不可能となります。
さらに撮影方法や画像解析に勉強と経験が必要となります。
●マイクロスコープ
マイクロスコープを活用した根管治療の有効性がしだいに認められています。
その理由として、これまでは直視できずに治療不可能であったトラブル症例でも、
根管口の確認、狭窄根管内の探索なども格段に向上しています。
さらに、穿孔部位確認や器具破折片の除去もマイクロスコープなしでは、
経験と勘に頼るしかありません。
歯根吸収歯などの拡大・形成、
さらに根管充填に際してもその有用性に驚かされます。
高名な歯内療法専門医も
「You can only treat what you can see」と述べています。
マイクロスコープで確認できないところに原因があり、
その結果、症状がどうしても消失しないトラブル症例では、根管内からの治療に限界があることになります。
長引く慢性疼痛や違和感を訴える患者さんでは、
根管治療歯ではなく非歯原性疼痛の可能性が高く、「痛み専門医」に紹介することも大切なのです。
●臨床に役立つ薬剤情報
根管治療の基本的考え方は、これまでの薬剤主流から機械的治療へと変更していますが、
最近、治療用薬剤としてバイオセラミック覆髄剤(材)のMTAと水酸化カルシウム製剤が臨床で好んで使用されています。
MTAは1990年代初頭に米国ロマリンダ大学で開発され、
ポートランドセメントをベースにしたケイ酸カルシウムを主成分とする生体親和性の高い材品です。
日本では覆髄剤として認可され、2007年頃から発売されましたが、
欧米では利用範囲は広く、覆髄、アペキシフィケーション、Revitalization、根管充填、逆根管充填材、穿孔部封鎖材として有効使用されています。
一方で、改良すべき点としては硬化するまでの時間が長いこと、
流動性に乏しく操作性がやや不良で、時間の経過にともない変色が発生することなどが指摘されています。
水酸化カルシウム製剤は、
その硬組織形成促進作用により覆髄剤あるいは根管充填剤(永久的および暫間的)などに使用されてきました。
本製剤の硬組織形成促進作用はその高いpHとされており、
その作用機序の詳細はすでに報告されています。
そこで、この高いpHに着目して、
欧米では唯一の根管消毒剤として専門医および一般歯科医師の間で有効使用されています。
拙著では、必ず臨床で遭遇するトラブル症例を提示し、なぜ失敗したかについて簡単に説明しています。
その内容は、ただ危機を煽るだけでなく、
明快かつリアリティをもった処方箋(治療法)が述べられていることです。
ぜひご参考ください。
日本大学歯学部前教授
鶴町 保
⇒ http://www.quint-j.co.jp/shigakusyocom/html/products/detail.php?product_id=3189